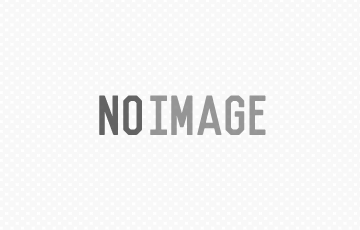歯科医院として集患できる方法を模索していませんでしょうか。「新規の患者さんの数が減少してきている」「新規の患者さんが来院しても通院がすぐに途絶えてしまう」といった具合に、患者さんの集患に頭を悩ます歯科医院が近年増加してきています。
では、患者さんが少ない、もしくは患者さんが減少している歯科医院はどういった対策をすれば集患できるようになるのでしょうか。今回は、集患を目指す歯科医院が施策すべき3つの簡単な対策をご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
目次
歯科医院が集患をしなければならない背景
集患方法を考えるにあたって、まずは歯科医院が集患しなければならない理由をみていきましょう。
歯科医院の倒産件数は20件に
歯科医院が集患しなければならない一番の原因は、やはり経営状態の悪化があります。近年、集患できずに倒産していく歯科医院が増加しています。
東京商工リサーチ「2017年度「歯科医院」の倒産状況」によれば、2017年度に倒産した歯科医院の数は20件で、2016年度と比較しておよそ2倍と大幅に増加したようです。歯科医院の倒産件数が20件に到達したのは1994年度以来とのことです。
また、歯科医院の負債額も増加しているようです。同調査によれば、2017年度の負債総額は11億500万円にもおよび、5年ぶりに前年度を上回る結果となりました。
上記のように倒産・負債を抱える発端には、競合の増加や過疎化が原因とされています。近年は患者の減少により経営状態が悪化する歯科医院が多く、集患対策を行わなければならない環境になってきています。
歯科医師・歯科医院の増加
歯科医院が躍起になって集患対策を進めるのには、競争率の激化が背景にあります。一昔前と比べ歯科医師及び歯科医院の数は増加しています。
まずは歯科医師の増加について考えます。厚生労働省「第 111 回歯科医師国家試験の学校別合格者状況」によれば、2017年の歯科医師国家試験合格者数は2,039人です。つまり、毎年2,000人前後が歯科医師として排出されているのです。もちろん、合格者全員が歯科医師になるとは限りませんが、年々新たな若い歯科医師が誕生しているのは確かです。
歯科医師の増加と共に、歯科医院の増加も顕著です。厚生労働省「医療施設動態調査(平成 30 年 1 月末概数) 」によれば、2018年1月時点での歯科医院の数は68,791箇所と、2013年1月時点の68,441箇所と比較して約350箇所も増加しています。歯科医院の倒産数は増加しているのに対し、歯科医院の母体数は増えていることから、歯科医院同士の一層の競争激化が考えられます。
こうした競争激化に備えて、現段階から集患対策を行わなければ、「気付いた時には既に間に合わない状況」になってきているのです。
歯科医院の集患に必要な3つのステップ
集患を目指す歯科医院が数多くいる中で、どうやって集患の差別化を図っていくのか。この章ではそのヒントとなる3つのステップをご紹介します。どの歯科医院にも当てはまる最も基本的なことを取り上げていますから、ぜひ集患対策の参考にしてみてください。
集患の対象を絞る
シンプルかつ効率的な集患を行うために、まずはじめに歯科医院がすべき対策は、患者さんのターゲットを絞り込むことです。
ご存知の通り、歯科医院を含む医療施設は、医療法によって広告規制を受けています(詳しくはこちらから)。ですから、多くの患者さんが歯科医院を選ぶ際には、歯科医院のホームページや近隣住人の評判、口コミを参考に決めます。これら全ての情報に共通していることが、「専門性のある場合に歯科医院の評価が高くなる」ということです。例えば、近隣住民の評判で考えてみましょう。歯科医院を進める時、「あの歯科医院はとにかく良いから行ってみて!」と話す方は少ないでしょう。それよりは、「親知らずの治療ならあの歯科医院が良いよ!」と評判になることが大抵です。
出来るだけ幅広い患者層を取り込んだ方が集患に繋がるような気がしますが、むしろ不特定差数に向けたは逆効果です。自身が得意な専門分野に絞って新規患者の集患を行うことこそが集患に向けた有効な手段なのです。
「どんな患者さんをターゲットに絞るか」によって歯科医院の専門性・方向性を決定することが集患に繋がるのです。ですから、集患対策を行う際には、「どんな患者さんにきて欲しいのか」と、患者さんの絞り込みから始めるようにしましょう。
治療後の経過を大切にする
既に対策済みの歯科医院も多いかもしれませんが、患者さんに長期間にわたって来院していただくシステムを構築することも集患へとつながります。「集患」と聞くとどうしても新規の患者さんに目がいきがちです。しかし、新規の患者さんの模索よりも既存の患者さんを大切にすることの方が大切です。
そして、既存の患者さんに長期間にわたって来院していただくためにも、定期的な来院の機会を設けるようにしましょう。定期的な来院を促すことで、治療後の経過を追うことができますし、歯科医院の経営も安定してきます。患者さんにとっても、定期的な診断で歯の予防を行うことができまから、まさにwinwinの関係が構築できます。
集患対策に乗り出す際には、新規の患者さんに目を向けるのではなく、まずは既存の患者さんを大切にし、経営の安定化を図りましょう。
価格設定を見直す
患者さんが歯科医院を決定する際に、腕の良さも指標の一つにしますが、それと共に大切なのが、診療の価格です。どんなに腕が良い歯科医院でも高価では効果的な集患を行うことはできません。価格を決定する際には、「3段階の価格設定」を意識すると良いでしょう。
3段階の価格設定とは、消費者心理をコントロールする手法の一つで、患者さんは真ん中の値段のものを自然と購入するというものです。
また、窓口負担の値段も重要です。窓口負担の値段が高いと、患者さんは「値段の高い歯医者」と考えます。一般的に5,000円以上の窓口負担は高いと考えられますので、3,000円未満に収まる程度の価格設定にすると良いでしょう。
関連記事
歯科医院は集患だけでなくスタッフの育成にも注力を
ここまで歯科医院の集患対策についてご紹介してきましたが、こうした集患対策を効果的に行うためには前提条件があります。それが、スタッフの知識量とやる気です。どんな集患対策にせよ、スタッフが一丸となって行うことで初めて効果を発揮します。逆に、スタッフの足並みが乱れていると、いつまで経っても効果的な集患を行うことはできません。
歯科医院の印象はスタッフの接客態度から生まれると言っても過言ではありません。いわば「歯科医院の顔」です。彼らの育成がままならなくては既存の患者さんは減少し、新規の患者さんは来院しないという負のスパイラルに陥ることでしょう。
そうならないためにも、スタッフの育成には注力しましょう。具体的には、以下のような方法で育成を行うと効果的です。
①スタッフ同士のミーティングを設ける
②スタッフ向けの意見箱の設置
③優秀なスタッフへの追加の賞与
集患対策とともに、是非スタッフの育成にも力を注いでください。
歯科医院の集患まとめ
今回は歯科医院における集患対策についてご紹介してきました。いかがだったでしょうか。
一昔前から「歯科医院は増加しすぎ」とされてきました。その影響を受け、近年では倒産する歯科医院が増加しています。こうした環境下でいかに生き残ることができるか。集患は死活問題だと言えます。
既に集患に悩んでいる歯科医院はもちろん、現在は好調で集患する必要を感じていない歯科医院も、ぜひこの機会に集患対策について考えてみてはいかがでしょうか。