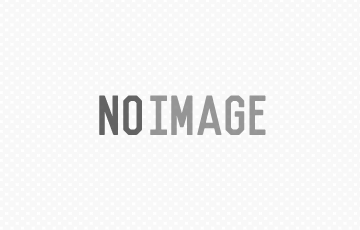歯科医院の多くは、「将来的なことを考えて、今のうちから増患対策を取っておきたい」と考えています。と言うのも、近年歯科医院を取り巻く環境は大きく変わっているからです。ズバリ言わせていただきます。これからの歯科医院は、増患に向け長期的な視点を持ち、適切なマーケティングを行なっていかなければ経営が立ち行かなくなることでしょう。では、どういった対応を行えば歯科医院の増患に繋がるのでしょうか。今回は、短期間での増患を達成している歯科医院が実際に行なっていることを例に挙げてご紹介していきます。
目次
歯科医院の増患対策の前に!置かれている現状とは?
歯科医院の増患対策の前に、まずは歯科医院が置かれている現状を見ていきましょう。現状分析ができていなければ、どんな増患対策やマーケティングも成り立ちません。
歯科医院の需要は年々減ってきている
まず、歯科医院の需要は年々減少傾向にあることを理解しておきましょう。増患を目指す歯科医院が多いのとは裏腹に、年々患者の数は減少しています。つまり、今後の歯科医院は限られたパイの中で、争うことになります。競争率が高くなっていくことは明白です。
患者が減少している背景には、日本の少子高齢化や人口減少が挙げられます。総務省が発表している我が国における総人口の長期的推移によれば、日本の人口は2050年時点で約9500万人にまで減少すると予想されています。さらに、高齢化率は同年で40%近くになると予想されています。このような急激な人口減少の中で、歯科医院の需要は年々減少しているのです。
歯科医師は年々増え続けている
人口が減少していることは前述した通りですが、反対に歯科医の人口は年々増加傾向にあります。少子高齢化や人口減少の影響で患者全体のパイが減っているにも関わらず、歯科医師の数が増加していることは、競争率のより一層の激化を表しています。いわゆる供給過多の状態です。
平成28年に厚生労働省が発表した医師・歯科医師・薬剤師調査の概況によれば、歯科医師数は年々増加しており、平成2年に74,028人だった歯科医師数は平成28年に104,533人まで増加しています。これは26年間で歯科医師が約1.4倍も増加したことを表しており、まさに日本の人口推移グラフと真逆の動きであることがわかります。このような急激な歯科医師の増加の中で、歯科医院の供給量は年々増加しているのです。
価格は需要と供給の均衡点で決定される
上記で説明したように、今後歯科医院は以下の2つの問題を抱えることは不可避だと言えます。
①人口減少により、歯科医師の需要は減少している。
②歯科医師の増加により、供給が過剰になりつつある。
経済学では、需要と供給が一致する均衡点で市場価格が決定されると言われています。これを踏まえて歯科医院の将来性を考えると、「非常に厳しい環境である」という事になります。歯科医院の需要は減少し、一方で供給は増加するため、結果として市場価格は下がるからです。もちろん、増患も日が経つごとに難しくなるのです。
増患対策は今すぐに始める
増患対策を後回しにしている歯科医院は「焦った時には時すでに遅し」という状況に陥る事でしょう。前述したように、増患対策は今すぐにでも始めるのが吉です。今この瞬間にも患者の総人口は減り、歯科医師の総人口は増えています。今日、明日からの行動が今いる患者を繋ぎ止め、新たな患者を呼び、ひいては歯科医院の増患増収に繋がることでしょう。
では、増患対策のためには具体的にどう行った対策やマーケティング手法を行うのが良いのでしょうか。次章から詳しく見ていきましょう。
関連記事
歯科医院が増患増収に成功するために行う3つのコト
ここからは本題である増患増収のために、歯科医院が今日からでも行うべき3つのコトについてご紹介していきます。
SWOT分析で自社の強みを明確にする
まず1つ目の増患対策が、SWOT分析を用いた戦略方針の決定です。SWOT分析とは、自社にとっての、S:Strength(強み)W:Weakness(弱み)O:Opportunity(機会)T:Threat(脅威)を明確にするマーケティング手法です。この手法を用いることで、他の歯科医院との差別化を図ることが出来ます。いわゆる、差別化戦略です。
差別化戦略は経営学では非常に有効な手段の1つであり、身近なところで言えば大手コーヒーチェーンのスターバックス、コメダ珈琲、ドトールのそれぞれの違いから学ぶことができます。3社はそれぞれ、価格や立地、顧客層などに強みを持ち、住み分けを行なっています。これは歯科医院の場合も同様で、近隣の歯科医院と強みや機会が被っていれば互いに競争する事になります。結果として増患には繋がりません。逆に住み分けが明確に区別されていれば、増患増収を見込むことができます。
そこで、歯科医院にとって最も有効的なSWOT分析は以下の2つです。
①機会と強みの2つを活かして、他の歯科医院と差別化を図る方法
②機会と弱みの2つから、自社の強化すべき課題点を洗い出す方法
この2点を考える事で、他の歯科医院との差別化を図り増患増収を目指すことができます。
歯科医院を可視化する
2つ目の増患対策が、患者にとって歯科医院をより身近に感じてもらうべく可視化させることです。ここでいう可視化とは、例えば以下のようなことを指します。
①医療設備を見せる
②診察室/待合室を魅せる
③患者の口コミを公開する
多くの患者は病院に対し、負のイメージを持っています。その負のイメージを払拭するためには、まずは患者に歯科医院の内部について知ってもらう必要があります。そのために、医療設備や診察室、待合室の雰囲気をネット上で公開することが有効です。総務省が平成28年に発表した情報通信白書によれば、スマートフォンの普及率は70%以上にまで上昇しています。今後も普及率は増加予想にあるため、インターネットを活用しない手はありません。さらに昨今はTwitterやFacebookといったSNSが発展していますから、こうしたツールを積極的に活用していくと良いでしょう。
さらに、患者の口コミを公開することも非常に有効です。特に40代〜50代の女性患者は口コミを重要視しますから、この層の患者を大切にすることが口コミ効果を助長する事になります。診察に訪れたことがない患者の歯科医院に対する負のイメージを払拭するために、上記のような施策に力を入れて取り組むと良いでしょう。
患者が信頼できる歯科医院づくりから始める
最後の増患対策が信頼できる歯科医院づくりです。増患と聞くと、どうしても新規患者やリピーターを重視しがちです。しかし、今いる患者を大切にしなくては本末転倒です。どんなマーケティング手法よりも、患者にとって居心地の良い歯科医院づくりを優先しましょう。
今いる患者との信頼関係を築くことで、地域住人の方々に歯科医院の価値を理解してもらうことが出来ます。歯科医院の価値を患者が理解すれば、来院する患者数は自ずと増加します。逆に言えば、上記で挙げたようなマーケティング手法や増患対策を行なっても、今いる患者を粗末に扱っているようであれば、増患は望めません。
では、患者が信頼できる歯科医院を目指すにはどんな施策を行えば良いのでしょうか。以下にまとめてみました。
①患者が喜んだ顔/不安げな顔をするのはどんな時か?
②患者からどんな質問を受けることが多いか?
③患者からのフィードバックを受ける態勢は整っているか?
④患者の待ち時間にまで気を配ることはできているか?
こうした問題に真摯に取り組み施策を考える事によって、自ずと歯科医院の強みが引き出されてきます。また、これらの問題に取り組むためには、スタッフとの連携や情報共有が必要不可欠です。そういった意味では、スタッフとの密な連携やスタッフのモチベーションアップも増患に向けた大切な対策の1つだと言えるでしょう。
関連記事
【必見】歯科医院が集患するための最もシンプルな3つのステップとは
歯科医院が増患増収に成功するポイントのまとめ
今回は歯科医院の増患増収に向けた対策法をご紹介してきました。いかがだったでしょうか。患者が求めていることは、個々人によって違いデリケートで複雑な問題に囚われがちですが、1人の患者の評価を高めることが歯科医院の評価を大きくあげるのです。
一気に増患を目指すのではなく、まずは今いる患者を大切にし、地域住民に愛される歯科医院を目指す、そのための対策をとっていただければと思います。